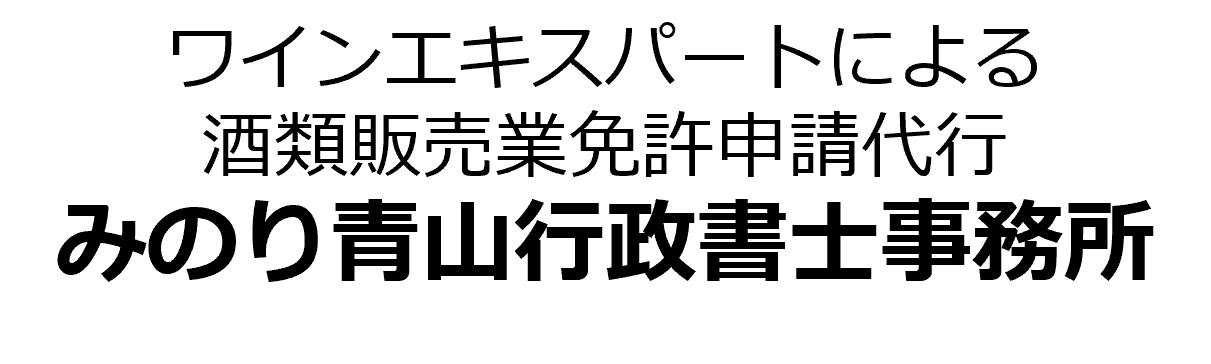1. 制度の“見えにくさ”と事業リスク
酒類販売業免許の取得は、単に「申請書を出せば許可される」というものではありません。
制度上の要件は酒税法や国税庁の手引で定められていますが、実際の審査では「販売場の状況」「経営の安定性」「取扱う酒類の種類」「販売ルート」など、個別の事情を踏まえた判断が行われます。
そのため、書面上は同じ条件でも、税務署によって運用や指導内容が異なることがあり、「何が通るのか」が見えにくいのが現実です。
また、免許を取得した後も帳簿の整備や報告義務などが継続して求められるため、“免許取得=ゴール”ではなく、スタート地点にすぎません。
とくに新規事業者の場合、税務署との対応や販売管理体制の整備まで含めて考えなければならず、これが「酒販免許は難しい」と言われる背景となっています。
2. 財務・過去実績・納税状況という“実力審査”
酒類販売業免許の審査では、形式的な書類だけでなく、経営の健全性や税務面の信頼性が重視されます。
特に、次のような観点から「安定して継続的に事業を行えるか」が審査対象となります。
・開業資金や運転資金の十分性
・過去の確定申告や納税状況
・借入の有無・返済状況
・事業計画の現実性や売上見込みの根拠
つまり、これは単なる“形式審査”ではなく、経営者としての信頼性を測る実力審査といえます。
過去に税金の滞納歴がある場合や、見込み数量の根拠が弱い場合には、免許が下りにくくなるケースもあります。
このように、酒販免許は「財務的に安定していて、税務署が信頼できる事業者」であることを証明しなければならない点が、難しさのひとつとなっています。
3. “場所”と“取引先”が鍵になる申請のハードル
酒販免許の審査では、販売場(営業場所)と販売先の適正性が非常に重要なポイントになります。
たとえば、販売場が飲食スペースと仕切られていなかったり、他事業と区分されていない場合、
「どこで小売を行うのか」が不明確として不許可になることがあります。
また、取引先の実在性や具体性も問われます。特に卸売免許を申請する場合、
販売先が明確に決まっていない、あるいは相手が酒類販売免許を持っていないと、
「販売の実現可能性が乏しい」と判断されることがあります。
さらに、バーチャルオフィスやシェアオフィスなど、実体のない事業所では原則として免許が認められません。
こうした要件は一見単純に見えますが、実際の現場では賃貸契約書や図面の区分方法、
販売経路の具体的な証明など、細かな書類整備と説明力が求められます。
つまり、酒販免許は「場所と相手が確実にある」ことを示せなければ通らない許可。
この物理的・実務的なハードルの高さが、申請を難しくしている要因の一つです。
4. 酒販免許を“難しい”で終わらせないために
酒販免許は、単なる申請書の提出ではなく、法令理解・事業計画・販売環境の整備が一体となって初めて許可される制度です。
そのため、「自分のケースに当てはめるとどの免許が必要か」「販売場の区分は十分か」「販売見込みをどう説明するか」といった判断を、
事業者だけで行うのは容易ではありません。
一方で、要件を正確に整理し、事前相談や書類作成を丁寧に行えば、免許取得は決して不可能ではありません。
実際、近年では小規模なワインショップやオンライン販売業者など、個人・法人を問わず新規取得の例も増えています。
酒販免許を「難しい」で終わらせないためには、“何が難しいのか”を正しく理解し、的確に対策することが何より大切です。
そのサポートを行うのが、行政書士など酒類販売業に精通した専門家の役割といえます。