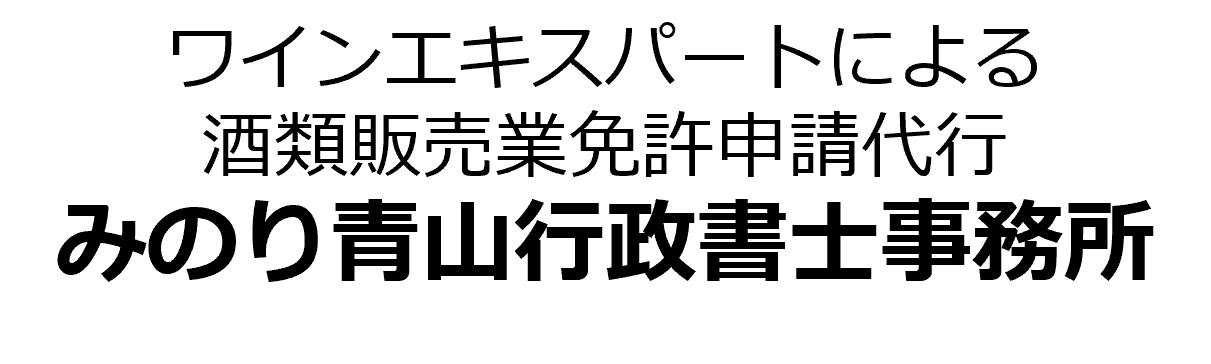酒類販売業免許とは
酒類販売業免許とは、お酒を販売する事業を行うために必要な免許です。
酒類は嗜好品であると同時に、酒税法によって厳格に管理される品目であるため、誰でも自由に販売できるわけではありません。販売を行うには、申請書を税務署に提出し所轄税務署長の免許を受けなければなりません。
この免許制度は、単なる営業許可という意味合いだけでなく、
- 酒税の確実な徴収
- 公正な流通秩序の維持
- 消費者保護
といった目的のもとに設けられています。
なぜ免許が必要なのか
酒類は他の商品と異なり、酒税が課税される特別な商品です。
免許制度を通じて、販売経路を明確にし、無許可販売や脱税を防ぐことが目的です。
また、アルコールは未成年者への販売禁止や表示義務など、社会的責任が伴う商品でもあるため、
販売業者には一定の信頼性や適正な管理体制が求められます。
このように、「酒類販売業免許」とは、単なる形式的な許可ではなく、公的な信頼の証でもあります。
酒類販売業免許の種類と違い
酒類販売業免許には、販売先や取引形態によって複数の種類が存在します。ここでは、主に事業者が取得を検討する「小売系」と「卸売系」の免許について、その違いを整理します。
小売系の免許
小売系の免許は、最終消費者に対して酒類を販売するためのものです。主に次の2種類があります。
一般酒類小売業免許
店舗などで消費者に対して酒類を販売する際に必要な免許です。販売対象は「店舗の近隣地域」に限られるのが特徴で、実店舗での対面販売を前提としています。コンビニエンスストアやスーパーマーケット、酒屋などが取得しています。
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログ販売など、通信販売の方法で酒類を販売する際に必要な免許です。全国の消費者に販売することが可能で、ECサイトやオンラインショップを運営する場合に取得が必要です。
なお、通信販売免許では「販売できる酒類の範囲」が限定される場合があるため、取扱品目に応じた確認が重要です。


卸売系の免許
卸売系の免許は、酒類を小売業者や飲食店などの事業者に販売するためのものです。販売先が事業者に限定される点が、小売系免許との大きな違いです。
全酒類卸売業免許
全ての種類の酒類を、他の事業者に卸売できる免許です。販売量や取引規模が大きい業者が対象となります。
ビール卸売業免許
ビール卸売業免許は、仕入れたビールを、小売店や飲食店などに卸売するための免許です。対象はビールに限定され、他の酒類を取り扱う場合には別途免許が必要です
輸出酒類卸売業免許
日本国内で製造された酒類を海外に輸出するための免許です。主に日本酒や焼酎などを海外の取引先に販売する事業者が取得します。
輸入酒類卸売業免許
海外から輸入した酒類を日本国内で卸売するための免許です。ワイン、ウイスキーなどの輸入酒類を飲食店や小売店に供給する業者が対象です。
洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許は、ワイン・ウイスキー・ブランデーなどの洋酒を、国内の小売店や飲食店へ卸売するための免許です。扱う酒類の範囲は免許申請時に限定され、ビールや日本酒など他の酒類を扱う場合は別途免許が必要となります。
製造と販売の関係
酒類の製造を行うには、別途「酒類製造免許」が必要です。製造免許を持っていれば、自社で製造した酒類を販売することも可能ですが、販売先や方法によっては、販売業免許の取得も必要となります。
- 製造免許のみでできる:その製造免許を受けた製造場内において、製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類の販売する
- 販売業免許が必要:製造場とは別に売店を設けてお土産用の果実酒を販売する
免許取得までの基本ステップ
準備段階
酒類販売業免許の取得には、事前の準備が非常に重要です。
スムーズな申請のために、以下の点を整理しておきましょう。
- 事業内容・販売形態の整理 どのような形で販売するか(店舗販売/卸売/通信販売など)を明確にします。免許の種類によって要件や必要書類が異なるため、早めの方向性決定が大切です。
- 販売場の確保 実際に酒類を保管・販売する「販売場」を確保します。バーチャルオフィスや共有スペースは原則不可とされており、独立した事業用スペースが必要です。
- 販売管理者の選任・研修受講計画 販売管理者は、酒類販売管理研修を受けた有資格者である必要があります。早めに候補者を決めて受講スケジュールを立てておくと安心です。
申請手続きの流れ
免許申請は、管轄の税務署で行います。おおまかな流れは次のとおりです。
- 書類作成・添付資料の整備 申請書類一式を整えます。販売場の賃貸借契約書、登記事項証明書など、多くの添付資料が必要です。場合によっては管轄の税務署に相談し、該当する免許の酒類や必要書類を事前に確認します。
- 申請書提出 書類が揃ったら、税務署の酒類指導官に提出します。書類不備があると補正を求められるため、事前の丁寧な準備が重要です。
- 審査(約2か月前後) 提出後は、酒類指導官による実地調査や確認が行われます。販売場や保管状況が要件を満たしているかがチェックされます。
- 免許交付・登録免許税の納付 審査を通過すると、免許交付の連絡が届きます。登録免許税(小売業免許で3万円)が納付された後、正式に免許証が交付されます。
- 開業後の帳簿管理・届出 免許取得後は、酒類の仕入・販売記録の保存や、販売管理者の研修更新などが必要です。営業開始後も税務署への届出義務があります。
ご依頼の流れ
当事務所では、申請から免許取得まで手続きの全工程を行政書士が一貫して代行いたします。お客様のご負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、以下の流れで進めさせていただきます。

みのり青山行政書士事務所
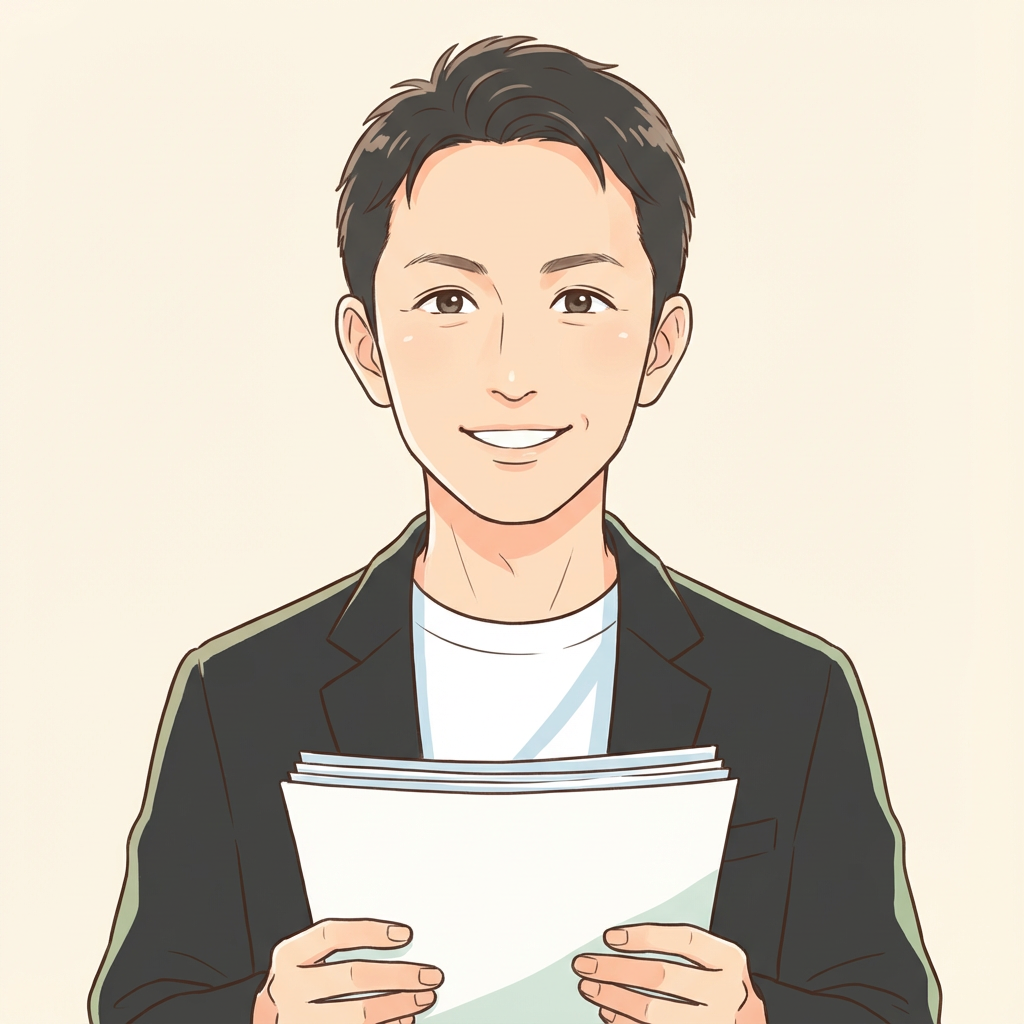
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。